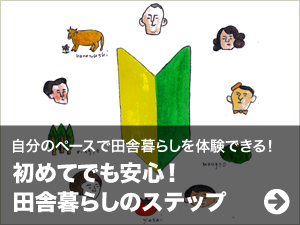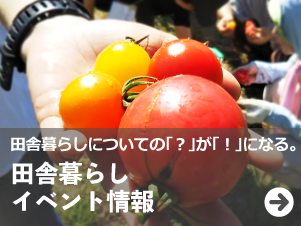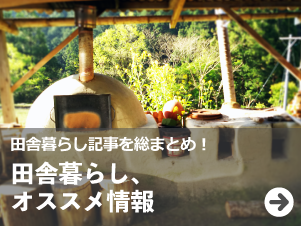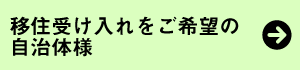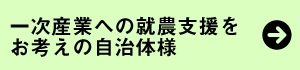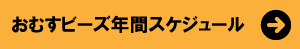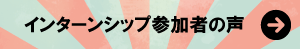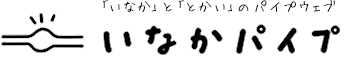地方の仕事は自分で創る!地方の仕事の作りカタ
地方へ移住し仕事を探そうとお考えの方へ!
実は、地方は「自分で仕事をつくりやすい環境」であるとご存知でしたか?
慢性的な人手不足の地方や田舎では、ハローワークや自治体などを通して企業で働くことはもちろん一つの選択肢です。その一方、都会では当たり前の「ちょっとした手助け」を求める人も多く、仕事が生まれやすい環境にもなっています。
そこで、地方の仕事事情をまとめ、実際のアイデアをもとに生まれた仕事などを紹介していこうと思います!

「地方に仕事はない」は間違いです。
私たちおむすビーズはこれまで様々な方の移住を支援してきました。
地方に暮らすスタッフもおり、現地の人と交流しつつ日々情報を集めています。
その経験から自信をもって言えることがあります。
「地方に仕事はない」という考えは間違いです!!
移住を考える方の中には
「地方に行ったら仕事がなさそう」
「地方で生活費が稼げるか不安」
という方がおられます。
住み慣れた街を離れ、新しい生活を始める。もちろん不安を感じて当たり前です。
その不安を少しでも軽減できればと思いますが、ひとつ言い切れることは、
「地方にも仕事はたくさんある!」
ということです。
実際に地方や田舎は様々な人手を必要としています。
荷物の配送や移動の送り迎え、ちょっとした農家の仕事のお手伝いなど、自分の空いた時間にできることが収入源となることも多く、人口が少ない地方だからこそアイデア次第で自分の居場所をつくることができる場面も多いのです。
もしも、移住を検討しているものの、不安の一つが「仕事」である場合は・・・思い切って行動してみてください。
情報収集はもちろん大切ですが、地域へ行く、話を聞いてみる、そんなことで多くのきっかけが生まれると思います。
地方での仕事の作り方
アイディアを形にした事例
KUSUBURU HOUSE(くすぶるハウス)※ゲストハウス
くすぶるハウスは、島根県隠岐の島にある古民家を改装したゲストハウスです。
田舎に家を買い、リノベーションし、民泊施設として営業する、移住者の理想の暮らしに近いこともあり近年多くなってきました。
1日1組限定となっており、観光客をターゲットに特別な体験を提供されています。

WEBサイト:くすぶるハウス
隠岐諸島は日本海に囲まれ、森林が豊かな島なので、一次産業にはもってこいの島です。
島暮らし、なんだかとても穏やかな日々が送れそうですよね。
もちろん島暮らしにもメリットデメリットがありますが(台風が来ると物資が途絶えるとか)、仕事に関しては春から秋にかけて観光関連のお仕事がたくさんあるのが特徴です。
また海に囲まれているため海産物の加工や出荷の仕事などが多いのも特徴でしょうか。
移住者が経営するゲストハウスは貴重な情報源です!
既存の事業を継承する
事業継承という方法もあります。
後継者不足を理由に黒字廃業する事業主が増えてきている実情があり、事業を継承してくれる後継者を探している地域もあります。
例えば、高知県移住ポータルサイト「高知家で暮らす。」では、サイト内で継業したい方と、継業してもらいたい方とをマッチングするための情報を掲載。
■高知家で暮らす。-継業したい-
事業継承という形での仕事に興味があれば、移住を考えている地域の移住ポータルサイトなどを検索すると出てくるかもしれません。
観光資源を発掘し、新しいサービスを提供する
地方や地域では、毎日見慣れた風景も都会から来た人にとっては観光資源!
地元の方は「こんなものが珍しいかねぇ?」と思うようなこと、あたり前すぎて見過ごしてきた風景、それに気が付くのは移住者だから。
実際、インターンシップ中に訪問した全く整備されていない観光スポットの写真を見せると「ここ、どこですか?」「見に行けますか?」と聞かれることも多く、地元の方に聞くと「行ったことない」と返されたりします。青々とした木々、澄んだ水、見慣れると当たり前になって、それが都会の人には特別だということに住み慣れた人は気付けない。
移住者目線が発揮できるところだと思います。
もちろん、地元の方とのタッグは必要不可欠だということは念頭に。

三樽権現の滝への壊れていた橋が2023年ついに新しくなりました
地域おこし協力隊から仕事をスタートする
移住を検討されていれば、「地域おこし協力隊」という制度を1度は耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?
「地域おこし協力隊(ちいきおこしきょうりょくたい)」は、
主に都会などから人を呼び寄せて、人口が減ったり活気が少なくなったりしている地域の応援をしてもらう取り組みのことです。
国(総務省)が制度を作っており、次のような特徴があります。
1.移住・定住の促進
•都市部に住んでいる人が、一定期間(通常1~3年ほど)地方に移り住み、地域の活動をサポートします。
•そのまま地域に定住(移住して住み続ける)する人も多いです。
2.地域に合わせた活動内容
•地域の課題や魅力に合わせて活動し、たとえば伝統文化の発信、農業・漁業の手伝い、地域行事の企画運営、商品開発・PRなど多岐にわたります。
3.自治体が受け入れ・サポート
•地方自治体が受け入れ先となり、協力隊員には活動費や住まいなどのサポートがあります。
4.目的:地域の活性化
•若者や新しい視点を呼び込むことで、地域の人々と協力しながら地域のにぎわいを取り戻すことが大きな目的です。
都市と地方の双方にとって、「地方の魅力を活かしながら新たな価値を生み出す“きっかけ”」となる制度が、地域おこし協力隊です。
地域おこし協力隊として活動する方の紹介
私たちが移住を支援した方の中にも、移住後地域おこし協力隊となった方がおられます。
移住前との違いや、移住後の暮らしについて話を伺いました。

プロフィール
大手肥料メーカーで約30年間、営業事務として勤務。
福利厚生面が整い、残業もほとんどない安定した環境に身を置きつつも、新しい挑戦や取り組みを提案しにくい社内の空気や、昔ながらの体制に違和感を抱き続けました。
30代の頃から行政書士などさまざまな資格を取得し、“今の状況を打開したい”という思いを持ち続けたものの、子育てがひと段落するまではと、希望する部署への配属も叶わないまま日々を過ごしました。
一方、プライベートではスポールブール選手として日本代表としての活動を継続。
そんな中、「このままでは終われない」という想いが高まり、子育てが落ち着いたタイミングで地方移住を決意。
現在は地域おこし協力隊の林業振興員として活躍中です。
協力隊の活動だけでなく、林業関連のアルバイト(草刈り、伐倒、支障木処理など)にも声がかかるようになり、可能な範囲で手伝いに出向いています。
地域おこし協力隊としての給与に加え、林業の技術を活かしたアルバイト収入も確保。
家賃や業務で使用する燃料費などの補助もあり、充実した毎日を送っています。
都会から離れ、豊かな自然の中で地域の活性化に貢献しながら、自らの可能性を広げる新たな挑戦に、やりがいを感じています。
移住後の家探し
地方移住にあたり、地元のNPOなどから物件を紹介してもらい、現在の住まいを見つけました。自分で物件情報を収集するのはなかなか大変でしたが、現地のNPOや行政の窓口に相談すると、空き家や貸家を持っている方とのマッチングや地域の暮らしの情報など、思わぬつながりが得られることが多かったです。
夏場のスケジュール
•4:30 起床
•5:40 出発
•6:00 ミーティング後、現場へ移動して作業開始
•9:00 休憩
•12:00 作業終了(+1時間ほど機材メンテナンス)
日差しが強く気温も高くなる夏は、涼しい早朝から作業を始めます。
林業の現場では、草刈りや伐倒作業など、体力を使う業務が中心。
炎天下での作業を避けるためにも朝の時間を有効活用し、昼過ぎには終了することがほとんどです。
•冬場のスケジュール
•6:00 起床
•7:40 出発
•8:00 ミーティング後、現場へ移動して作業開始
•12:00 昼休憩
•13:00 作業再開
•15:00 休憩
•16:30 作業終了(+1時間ほど機材メンテナンス)
冬は日照時間が短く、朝が明るくなるのも遅いためスタートを少し遅らせます。夏場よりも寒さが厳しく、雪が降る地域では除雪や融雪など、季節ならではの作業が加わります。
地方起業のメリット・デメリット
いくら田舎で土地が安くても、単なる思いつきでお店をやるのは起業家からみたら無謀だと言います。
都会と同じ感覚で田舎でお店を開いてはいけません。
理由は、必要とする「人」が少ないからです。
田舎の人の習慣を変えるというのは相当な事。始めは物珍しさで来たとしても、長くは続かないでしょう。
田舎で事業をはじめる時のコツは、地域の特徴やメリット・デメリットを理解しておくことにあります。
地方で起業するメリット
・家賃が安い
・土地が広い
・人件費が安い
・環境がいい
・特産、名産品がある
地方で起業するデメリット
・人が少ないため消費も少ない
・車が必需品
・都会よりも物の調達にコストがかかる
・新しいものを受け入れづらい
逆に成功している方は、地域に必要とされている「モノ」をリサーチ出来ている、つまりきちんと計画的に起業された方と言えます。
地域で暮らしていると、「これがあればなぁ」や「こんなのがあれば利用したいんだけど」と言った地元の方の声が聞こえてきます。そう言った声をヒントに、自分なりの地方の仕事を見つけてみてください。
まとめ
田舎で起業するのはいいアイデアです。重要なのは「何をやるか」。
田舎の人からすれば「いらないもの」も、視点を変えれば「いるもの」に変えることも可能です。
ここでちょっと余談ですが、アワビがとれなくなったというニュースがありました。
アワビが取れなくなった理由はムラサキウニとやらが増え、アワビのエサになる海藻を食べつくしてしまったからだそうです。しかもこのムラサキウニ、とってもまずいらしく漁師さんからすればただの厄介者。つまりほんとうにいらないもの。
けれども、そこに誰かが目をつけ、その大量にいるムラサキウニの養殖をはじめます。
キャベツを与えたり、ウニを太らせたりと試行錯誤のうえ、甘みのある美味しいウニへと変化させます。
どうしようもなかったはずのただの厄介者にすぎなかったムラサキウニがお金に変わろうとしているのです。すごいですね。
行ってみないとわからないメリットデメリットがあります。
そもそも、メリットもデメリットも最終的には自分で決めるもの。
ある程度情報収集してしまえば移住したい場所へ自分の足で行ってみるのが良さそうです。
自分にしかわからないメリットデメリットを探しだし、ヒントを得る旅に出かけましょう!